このコーナーでは、チベットにまつわる様々な書籍などをご紹介しています。今回は登山家の渡部秀樹氏に、ご自身の著書『西藏系出雲族の伝説』をご紹介いただきます。
チベットを百回以上訪れた著者が、出雲での原体験と照らし合わせながら綴る不思議な縁の物語。登山と探査、そして祖父の記憶を通じて結ばれていく、出雲とチベットの意外な接点にご注目ください。
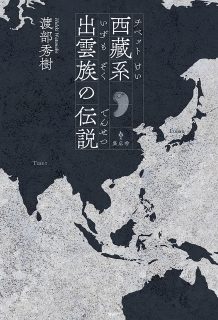
西藏系出雲族の伝説
チベットの登山や探検に関わっていると、地元の人々との間に信仰上のトラブルが発生する場面に度々遭遇し、「チベットの登山における信仰上の課題」について考察し、登山界に啓蒙する必要が生じました。それが「山から見たチベット仏教」についても学ぶことになるきっかけでした。チベットの登山や探査を行っている中でチベット民族に何となく明治の出雲人の面影を感じていた私は、中国による支配、近年の大開発がチベット奥地の伝統的な暮らしの中にも徐々に進んで行く様子を見てきました。外部と閉ざされチベット仏教に根ざし土地の神山「ユラ」を崇めながら何百年も自給自足で暮らしていた人々が、一気に市場経済や大開発のうねりに巻き込まれて翻弄されていたのです。それは、故郷を捨て離れた自分が出雲族としての伝承を絶やしつつある最後の世代かもしれないということに気付くことになりました。
幼少期に祖父から出雲族の口伝について断片的に聞かされていました。出雲が大和に國を譲った神話は、出雲族にとっては歴史として語られています。ある日突然、幼少期に祖父が勾玉に関しチベットと関連する話をしていた記憶がよみがえったのです。これを探ることが出雲でのフィールドワークとなりました。
出雲神族は祖神の魂の具象化である勾玉を持っており、これを伝える家系を「財筋」と称していました。そしてオオクニヌシの生誕と死が我が出雲族のアイデンティティに大きく関係していることを知ることになります。親族が、明治時代末期に大陸浪人となり、民族の独立や講和の象徴として、勾玉を威信財として用いてチベット独立に関わった可能性が出てきました。それは明治末期のあるチベット潜入者に託されます。その探検者の足取りを追ううちに、明治期と現在の出雲とチベットが縦と横の糸を紡ぐかのように、どんどん広がりを持って繋がっていったのです。
と、ここで終わるつもりで筆を進めていたのですが、最近になってチベット遊牧民から新たな事実を知り、前代未聞の運命の結末に辿り着きました。新たな伝説としてここに記録することにしました。
ナビゲーター/渡部秀樹(登山家)
『西藏系出雲族の伝説』(著)渡部秀樹/集広舎刊
2024年2月23日 発売、新書判・並製218ページ、1,818円(税別)
ISBN978-4-86735-052-2








